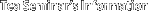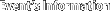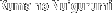ダージリンの茶園巡りのラストは、テライのグルマ茶園です。

標高2000mを越えるダージリンの街から南東へ約60km、標高500m以下の紅茶の産地テライへ移動すると、茶畑の景観も気温も違います。テライは平野でCTCの紅茶を生産する茶園が多く、グルマ茶園もそうです。


グルマ茶園はマハナンダ・ワイルドライフ自然保護区の南西約6km、ダージリンの玄関口であるバグドグラ空港まで約20kmに位置し、当時はイギリス人のオーナーが多い中、1886年にインド人が開設しました。現在のオーナーは4代目です。面積は約700ha、主にCTCのお茶を年間7億杯生産しています。


1日に4回摘んで来た茶葉を計量しており、プラッカーが摘んだ茶葉が入っている袋は、計量後ベルトコンベアーのような機械で運ばれて行きます。


この工場の萎凋槽は1階のオープンスペースにあります。ダージリンと比べて葉が大きいです。


大きな7連のCTC機で8種類のグレードを製茶していて、発酵前(左)と発酵後(右)の茶葉を見ることができました。色の変化がはっきりわかります。


工場見学後、4種の紅茶をテイスティングさせて頂きました。でもなぜかCTCのリーフではなく?工場の外には、乾燥機で使用する薪が置いてあります。
リシーハット茶園から北に約3km、かつてオレンジ畑であったことから名付けられた、オレンジバレー茶園があります。


標高1800〜730m、面積347ha。鉄鋼製造、不動産、風力発電所なども手掛ける、ダージリンに5つの茶園を持つBagaria グループが2001年から経営しています。



BIO、HAACCP、UTZ、ETP、COR、NATURLAND、JAS、レインフォレストアライアンス、フェアトレードの認証を受け、




ダージリンティーの品質を保つ為、昔からの機械を使用しています。



工場見学後、!st、2nd、オータムナルと2種類ずつ6種の紅茶をテイスティングさせて頂きました。推しは旬のオータムナルです。
ダージリンの茶園を巡る旅の後半は、ダージリンの街から西へ約10km、標高約1500m、面積約256ha(総面積388ha)のリシーハット茶園へ向かいました。下の写真は茶園からの眺めです。

リシーハットは現地の言葉で、穏やかな場所、聖なる場所、穏やかで平和な場所を意味します。サングマ、プッタボンなどのダージリンの茶園の他、インド国内の各地にも多くの茶園を持つJAY SHREE TEAが、1995年から経営しており、BIO(ビオ・バイオオーガニックの意)茶を生産しています。ISO、HAACCP、NPOP、POP、JAS、フェアトレードの認証も得ています。

敷地内にはシヴァ神とガウリ神のお寺(上の写真)もありました。


工場見学の後、茶畑も見学させて頂きました。



かなりの傾斜地ですが、摘み手の女性たちは重いカゴを背負いながら普通に歩いています。お茶だけではなく、観賞用の植物やフルーツ、スパイス等も生産販売し、従業員達の収入源を増やしています。


上は工場の入口。下は茶園への道の途中にある、WE LOVE RISHEEHAT の撮影スポット。

ダージリン・ヒマラヤ鉄道の駅にも、同じような撮影スポットがあります。